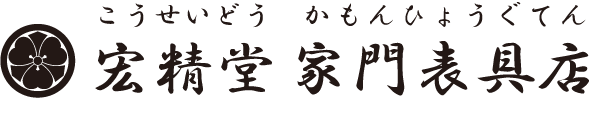伝統的な和襖製作の工程

伝統的な構造でつくられた和襖の作り方を骨下地から仕上げまで順を追って紹介します。
和襖は、骨下地の選定から、下貼り、建て合わせ、中貼り、上貼り、仕上げまで、多くの時間と手間をかけて1枚1枚作り上げます。
和襖は本襖とも呼ばれます。
骨下地から仕上げまで
-
- 骨下地【ほねしたじ】
-
周囲の框と中子で障子のように組んだ木製の骨地。
一般的な大きさの襖で、中子の数は 縦3本 横11本 が標準です。
この骨下地に下貼りを施すことで本襖の下地を作ります。
-
- 骨縛り【ほねしばり】
-
下貼りの工程で第1段階の貼り方です。
障子とは違い、骨に濃い糊をつけ、紙を貼ります。
骨縛り用には、手漉き紙、茶塵、桑塵などの強い和紙を用います。
-
- 胴貼り【どうばり】
-
下貼りの第2工程です。
骨縛りをした後に行うもので、光線による襖の透けなどを防ぐために行います。
打ち付け貼り、透き止めとも言います。
-
- 蓑掛け【みのかけ】
-
下貼りの中間の工程で、蓑のような重ね貼りとなるため蓑貼りとも言います。框の部分にだけ糊をつけて上へ上へと貼ります。
2枚が重なるものを二遍貼り、3枚が重なるものを三遍貼りと言い、最高八遍貼りまであります。(もっと多く重ねることも可能です)
蓑掛けに使う紙はそれほど上等なものは必要ないので、昔から反故という古い和紙(古文書や手紙、大福帳など)をつなぎ、裏返しにして使っていました。この反故、昔は紙が貴重だったから、要らなくなった紙を捨ててしまわずに裏返しにして襖の下張りに再利用したのでしょうが、今は古文書としての価値の方が高くなって、本物の反故を確保するのが難しくなっています。そこで、現在では代用反故として新しく漉かれた和紙を使う事が多くなってきました。
-
- 蓑押さえ【みのおさえ】
-
下貼りの最終工程です。
接着する全面に糊をつけ、蓑を押さえることから「ベタ貼り」とも言います。
これで本襖の下地は完成です。
この下地を持って現場に行き建て合わせを行います。
-
- 耳梳き【みみすき】
-
蓑押さえが済んだ段階で、現場で建て合わせをし、その寸法に合わせて角を落とし、框を削った後、下貼り段差を調整するために行う工程です。
耳梳きが終わると中貼りの工程です。
-
- 下浮け張り【したうけばり】
-
浮け張りとは、紙の周囲にだけ糊をつけて貼る工程です。
上貼りを浮かせた状態で柔らかく見せ、張り替えを容易にするために行います。
内部は浮いた袋状になるので袋張りとも呼ばれます。
1度目の浮け張りを下浮けまたは下袋と言い、小判の和紙を棒接ぎにして張ります。
-
- 上浮け張り【うわうけばり】
-
2度目を浮け張りを上浮けまたは上袋と言います。
上浮けには喰い裂きをした石州紙などを用います。
上貼りの紙の材質によっては、縦に接いだ喰い裂きの跡が目立つものもあるので、場合によっては横にのみ接いだり、上浮けの上に全面に薄い糊をつけた紙を貼る清貼りを行ったりすることもあります。
中貼りが終わると、いよいよ上貼りの工程です。
-
- 上貼り【うわばり】
-
最後に表面に襖紙を貼る工程です。
貼る材料はいろいろありますが、襖の場合は絹、麻、綿などの布や、「鳥の子」をはじめとする和紙がほとんどです。
下貼り・中貼りのあと仕上げとして美しく、皺がよらないように四辺を濃い糊で貼り、乾燥してピン張るように素材に応じた特殊な技術を駆使しています。
-
- 縁打ち【ふちうち】
-
最終の仕上げ工程。縁を打って引き手を入れたら完成です。
「襖の種類」で紹介した「チップボール襖」「ペーパーコア襖」「単板襖」は、下貼りの工程(1~5)を省略することで「和襖」と比較して手間とコストを抑えています。
ここで紹介した中貼りの工程(7~8)は二重浮けですが、茶塵紙で上袋のみを行う一重浮けや、上貼りの裏面に茶塵紙を貼って浮かせて貼る工法もあります。(以上を総称して「袋張り」と呼び、工法の違いは上貼りに使う襖紙の材質によって使い分けます)
また、当店では行っていませんが、中貼りの工程を全て省略し、襖紙の裏面全体に水を塗って紙を伸ばし、耳梳き(工程6)を終えた下地に直接貼る「水張り」という工法もあります。
なお、張替は上貼りと中貼りをはがして耳梳き(工程6)を終えた下地に戻し、中貼りからやり直しますので、中貼りのことを一般的に「下張り」と言う表具師さんも多いです。