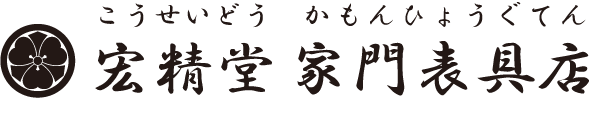衝立について
歴史を紐解くと

『障子について』のページでも述べましたが、『障子』という言葉が日本の書物に初めて登場するのは伝存する日本最古の勅撰の正史である『日本書紀』で、西暦645年に中大兄皇子、中臣鎌子らが宮中で蘇我入鹿を暗殺した「乙巳の変」を描いたシーンです。
- 日本書紀巻第廿四 皇極天皇四年六月
- 是日、雨下潦水溢㆑庭、以㆓席障子㆒覆㆓鞍作屍㆒。
- 現代語訳
- この日は大雨が降り、庭は水で溢れていた。庭に投げ出された鞍作(蘇我入鹿)の死体は、席障子で覆いをかけられた。
佐伯子麻呂と葛城稚犬養網田に斬殺された蘇我入鹿の遺体の目隠しに使われたのが席障子という衝立の一種です。(当時は、物の隔てに立てて遠望を妨げる建具衝立類の全てを「障子」と呼んでいました)
衝立が『衝立障子』と呼ばれるようになったのは、現在の襖・障子の元になった『遣戸障子』が生まれた頃と思われます。皆さんが御存知の「枕草子」の中にも、『衝立障子』が出てきます。
- 人の家につきづきしきもの
- 人の家につきづきしきもの 肱折りたる廊。円座。三尺の几帳。おほきやかなる童女。よきはしたもの。侍の曹司。折敷。懸盤。中の盤。おはらき。衝立障子。かき板。装飾よくしたる餌袋。からかさ。棚厨子。提子。銚子。
清少納言によると衝立は、平安時代中期には人家になくてはならないものだったんですね。