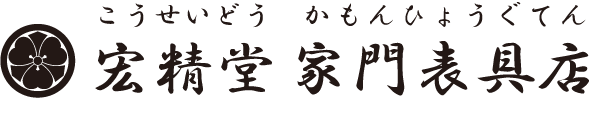和額について
歴史を紐解くと

日本における額の歴史は、お寺の山門や本堂、神社の鳥居や拝殿などの高い位置にその建物や寺社名を記した木彫の扁額に始まります。
扁額は遣隋使・遣唐使を通じて奈良時代には佛教建築とともに中国から伝わったそうですが、現在のような紙や裂を使った和額が誕生したのは江戸時代だと言われています。(桃山時代までの文献には、扁額以外の額に関する記述が無いそうです)
江戸時代初期に表装の技術も著しい発展を遂げ、江戸中期には一般庶民にとっても書画が身近なものとなる中で、室内に掛けるものとして紙や裂を使った和額が一般化しました。
明治時代に入り、西洋文化の流入によって一般住宅も洋風化すると、床の間がなくてもかけられる額の方が掛軸よりも好まれるようになり、現代の美術表装を代表する分野として発展し続けています。