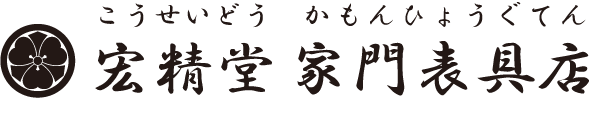屛風について
歴史を紐解くと

屛風の原型となるものは漢の時代に風除けの道具として中国で生まれ、朝鮮半島(新羅)を経由して686年に日本に伝わったとされています。しかし、ここで言う屛風は、複数の衝立を綴じ紐でつないだもので、現在のように和紙や絹で蝶番を作り前後に開閉ができるようになったのは鎌倉時代のことです。
この屛風は日本独自のもので、室町時代以降は輸出品として珍重され、遣明船による日明貿易で金屛風が多く輸出され、これにより、明では日本の屛風を「軟屛風」と呼び、中国古来の風除けとしての屛風を「硬屛風」と呼んで区別していたという記録が残っています。(以下、当サイトでは日本独自の「屛風」(軟屛風)について解説します)
なお、「びょうぶ」の表記は、正しくは「屛風」ですが、「屛」の字が常用漢字ではないので、一般には簡易慣用字体の「屏」を用いて「屏風」と書かれることが多いですが、当サイトでは一部を除き、本来の「屛風」という表記にしています。閲覧に支障がある場合はご連絡ください。